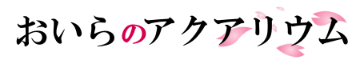水槽立ち上げ!PHモニター設置編
昨日、新規に立ち上げている「カエルアンコウ水槽」に海水を注入しました。
現在、海水をまわしている状態です。
サンゴ砂は敷いていますが、
生体、ライブロック、バクテリア、添加剤等は入れてない状態です。
スポンサーリンク
よく「新しい人工海水をなじませる」何て言い方をしますが・・・
おいらの場合は、自分自身の「ちょっと一息」・・・と言った方がいいかもしれません。
水槽の立ち上げ作業は、何てことありませんが・・・(肉体労働を除いて・・・)
慣れない、ブログの記事を書く作業や、写真をアップロードする作業で、
あっぷあっぷの状況ですので・・・・
でも、ネタ切れではありませんよ!!
書きたいことはたくさんあります。
と言うことで、今日行った「PHモニター」設置作業について・・・
あっ、そうそう・・・
海水魚で「PH」という言葉は、
酸性・アルカリ性を表す「ペーハー」という意味で使う場合と、
「パワーヘッド」という水流を作るポンプを略して使う場合が
あるので、混乱しないようにしましょう。
この記事のPHは、「ペーハー」の方ですから・・・・
混乱するのは、おいらだけかな・・・
スポンサーリンク
では、
前置きとして、PHについて、おいらの知っていることを・・・少々
(詳しいことを知りたい方は、専門書等で調べて下さいね。)
PH(ペーハー)とは、酸性とアルカリ性の度合いを表すもので、
0(ゼロ)から14までの数値で表します。
簡単に言えば、・・・
PH=7が中性
PH=7よりも数値が小さい場合は、酸性の度合いが強くなり、
PH=7よりも数値が大きい場合は、アルカリ性の度合いが強くなります。
ちなみに、テトラの試薬の説明書には、海水魚はPH値「8.0~8.6」ぐらいが適していると書かれています。
この、海水魚の理想的なPH値については、
海水魚の水質関連商品の説明書によって、かなり違います。
「8.0~8.2」が理想的と書かれていたり、(デルフィス)
「8.2~8.3」を維持するように書かれていたり、(シーケム)
します。
おいらも海水魚を飼育し始めたときには、どれを信じていいのか悩んだものです。
でも、今ではあまり神経質にならず、生体の状態を見ながら・・・・
PHの値が徐々に下がり始めたら、水換えの時期が近づいているという目安にし、
その水換えによって、急激なPH変化が起こらないようにしようと心がけています。
※水換えにってPH値は、少し上がります。
PHの測定は、試薬を使う方法かPHモニター(PHメーター)で測る方法が一般的です。
ちなみに、これが、テトラのPH試薬(ペーハーマリン試薬)です。

テトラのPH試薬には、淡水用もありますので、購入時は確認しましょう。
おいら、間違って淡水用を買ったことがありますので・・・
中身は、こんな感じです。
PH試薬は、測りたいときに海水を抜き取り、試薬を垂らして測らなければなりません。
なので、おいらは、常時PHを測定できるPHモニターを使用しています。
それが、これ・・・AIネットの「phモニター P-2」です。
中身は、こんな感じです。
で・・・
このPHモニターを正確に使うためには、「校正」という作業が必要です。
でも、簡単ですよ!
「校正」には、「校正液」を使います。
黄色い校正液をキャップに8分目入れ、電源が入った状態のセンサーを浸け、10秒待ちます。
その後、本体の「CAL」ボタンを1回押すと校正モードになるので、ここでもう一度「CAL」ボタンを押します。
あとは、自動的に校正してくれます。
校正しているところの写真です。
この後、センサーを一度よく洗い、ピンクの校正液でも校正を行います。
(何も考えずに、説明書に書いてあるとおりにするだけです。)
これで、校正は完了です。
ちなみに、このように、2つの値で校正することを2点校正と言います。
あとは、水槽への設置ですが、おいらの設置の仕方が悪いのか
付属のキスゴムだけを使用した場合、センサーが水没したことが何度かあるので、
エーハイムのクリップ付吸着盤12/16φ)をセットしました。

エーハイムのクリップ付吸着盤(12/16φ)をセットした状態
水槽のコーナーカバー内に設置しました。
ただいまのPHです・・・
今日も、実際の作業よりもブログを更新する作業に時間を費やしたような気が・・・
では、また!
スポンサーリンク